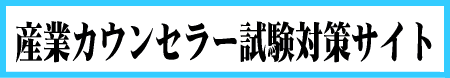<カウンセリングと隣接領域>
| 特徴 | 比較 | |
| ソーシャルワーク |
高齢者、子供、身体障害者 専門的福祉活動 日常生活指導 社会保障援助 介護、リハビリ |
コミュニケーションによる心理的援助 |
| 宗教 |
生き甲斐 幸福感 安心感 絶対者への帰依 教理、教義 |
生き甲斐 幸福感 本人自身が決める 教理、教義なし |
| 教育 |
個人の成長、育成を図る点 社会人、組織人として育つこと=社会化 知的面← |
個を尊重しのばす →情動面 |
| 人事管理 |
人を育て組織目標を達成する 雇用管理(能力開発)のほかに報酬管理、労務関係管理 |
自律した個人 |
<カウンセリングの限界>
| カウンセラー側 | クライエント側 | 両者 | |
| ① | 知識不足、技能不足 | モチベーションの不足 | 家族関係による |
| ② | 臨床体験の不足 | 知識能力の不足 | 役割関係による |
| ③ | 理論的固執 | 病態水準 | 利害関係による |
| ④ | 対応人数の限界(時間の制約) | 環境要因による限界(時間、距離、職場理解など) | 相性による |
<カウンセリングの効果>
| 直接的な効果 | 間接的な効果 | |
| 1 | 症状の消失 | 不平不満の解消 |
| 2 | 人間関係の改善 | 適性、能力の把握 |
| 3 | 自信が持てるようになった | 欠勤者の減少 |
| 4 | 生き方が楽になった | 定着率の向上 |
| 5 | こだわりが少なくなった | 生産性の向上 |
| 6 | 積極的に問題と向き合える | 職場活動の活性化 |
| 7 | 企業への信頼感、安心感 |
カウンセラー、クライエント、第三者での評価が必要
CL本人がよくなったという認知
カウンセリングを受けた甲斐があったという実感(主観でよい)